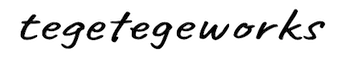2013年4月〜2018年3月まで裁判所事務官(一時期は検察審査会事務官も兼務)として勤務し、現在はライターをしているみさちゅーです。
勤務当時の情報にはなりますが、裁判所事務官志望の方・公務員試験を控えている方に向け、裁判所職員の内部事情や仕事内容などをご紹介しています。
今回は、裁判所事務官・裁判所書記官をはじめとする裁判所職員のリアルな福利厚生事情についてご紹介します。
手当ては手厚い。通勤・住居・扶養・超過勤務手当を完備
〈諸手当〉
期末・勤勉手当 1年間に俸給月額などの約4.3か月分
通勤手当 6か月定期券の価額等
(1か月あたり最高55,000円)
住居手当 月額最高28,000円
扶養手当 配偶者月額6,500円等
超過勤務手当等休暇等
裁判所職員(裁判所事務官・裁判所書記官など)になり、条件を満たせば通勤手当・住居手当・扶養手当・超過勤務手当制度が利用できます。
裁判所職員の通勤手当は、短距離での電車・路線バス通勤なら困らない程度

通勤手当は毎月最高で55,000円支給されるので、路線バスや電車での短距離通勤であれば十分まかなえるでしょう。
私も路線バスで通勤していましたが(乗車時間20〜30分程度)、通勤手当が足りないと感じたことはありませんでした。
新幹線・特急での長距離通勤の交通費はまかなえない可能性も
ただ、新幹線や特急での長距離通勤を行う場合は、全てをカバーするのは難しいところです。
異動がなかなか叶わず、やむを得ず特急で他の都道府県から通勤している方がいらっしゃいましたが、さすがに毎月赤字だとお話されていました。
■裁判所職員(事務官・書記官)の転勤事情。異動の間隔や範囲、打診時期などについても紹介
住居手当は官舎に住まないことが前提

住居手当については、官舎に住まない場合で条件を満たすと支給されます。
ここだけ聞くと官舎に住まなければ損した気持ちになってしまいますが、その分、官舎はリーズナブルな価格で住めることが多いです。
\裁判所事務官の官舎事情についてはこちらから/
超過勤務手当はよほどの時だけ申請している印象

超過勤務手当は、超過した日時などを自分で記入・申請するのがルール。
部署によりますが、ほぼ毎日残業をしている方でも、特別な事情がない限り申請している方は少ない印象でした。
超過勤務が多いといろいろ言われる場合もあるので、申請を避けることが多いのだと思います。
休日・休暇
〈休日〉
土・日曜日及び祝日等
〈休暇〉
年次休暇 年間20日(4月1日採用の場合、採用の年は15日、残日数は20日を限度として翌年に繰越し)
特別休暇 夏季休暇3日、結婚休暇5日、産前休暇、産後休暇、子の看護休暇、ボランティア休暇、忌引等
病気休暇
介護休暇
介護時間
当直・日直制度のない裁判所なら土日は自由に休める

当直・日直制度のない裁判所なら、土日は自由に休めます。
当直・日直制度がないのは、主に小規模な支部。
地裁本庁や都道府県内で大きめの支部では、当直・日直制度を設けている場合がほとんどです。
しかし、当直・日直が割り当てられるのは数ヶ月に1回程度ですので、基本的にはお休みできることになります。
\裁判所事務官の当直・日直制度についてはこちら/
年次休暇・特別休暇・病気休暇など、休暇制度も充実

裁判所には、年次休暇・特別休暇・病気休暇など、さまざまな休暇制度が設けられています。
部署や仕事の状況によってはなかなか取得できないこともありますが、前もって周囲に伝えておけば取得できることがほとんど。
よく聞いていたのは、年次休暇(いわゆる有給休暇。裁判所内では「年休」と呼ばれます)や、夏期休暇・結婚休暇・産前休暇・産後休暇などの特別休暇です。
育児休業も可能。1年程度休業する方が多い印象
〈育児休業〉
3歳に満たない子を養育するため、一定の要件のもとにその子が3歳に達する日までの希望する期間、休業が認められます。
裁判所職員(裁判所事務官・裁判所書記官など)は育児休業も可能。最長3年間の取得が可能ですが、手当てが出るのは1年間です。
このため1年程度休業し、復帰する方が多い印象でした。

ただ、最長期間である3年間丸々お休みされていた方・育児休業期間中に2人目を妊娠され、結果的に3年以上育児休業をされていた方もいらっしゃいます。
特に1年で復帰しなければ!という空気が流れている訳ではないので、ご家庭の事情に合わせて申請できるかと思います。
【元裁判所事務官が執筆】裁判所事務官の結婚事情。裁判官や司法修習生との結婚も
裁判所職員・国家公務員用の共済制度も利用できる

裁判所職員(裁判所事務官・裁判所書記官など)になると、裁判所職員や国家公務員用の共済制度が利用できます。
医療保険・年金制度は共済制度によるもの
福利厚生共済組合制度が設けられており、職員とその家族の生活の安定と福祉の向上を図るために、医療保険及び年金制度が用意されています。
医療保険・年金制度は「福利厚生共済組合制度」によるもの。
医療保険については、特記すべきは裁判所職員(裁判所事務官・裁判所書記官など)になると、黄色の保険証が付与されること。一般的な社会保険の保険証とは見た目が異なります。
また、年金制度は厚生年金のことで、以前は共済年金と呼ばれていました。
福祉事業も利用可能。プライベートの旅行代が安くなることも
裁判所共済組合や国家公務員共済組合連合会が運営する各種の福祉事業を利用することができます。
裁判所職員(裁判所事務官・裁判所書記官など)は、各共済組合による福祉事業も利用できます。
北海道から九州まで展開されている関連ホテルが安価で宿泊できる特典もあり、プライベートの旅行代を抑えたいときにも便利です。
そのほか、カニやお肉といった特産品の通信販売なども行われています。
【元裁判所事務官が解説】裁判所事務官の土日の過ごし方。 同期との関係性や共済組合の土日の集まりについても
裁判所職員の福利厚生事情をもっと詳しく知りたい方におすすめの本

裁判所に20年勤務され、現在は行政書士としてご活躍中の中村圭一さんが書かれた1冊です。

裁判所で働いたからこそ分かるリアルなお話が、良いこともそうでないことも詳しく綴られており、裁判所事務官時代の思い出がよみがえりました。
 厚みも程よく、章で細かく区切られているので、知りたい情報が書かれたページへアクセスしやすいのも特徴です。
厚みも程よく、章で細かく区切られているので、知りたい情報が書かれたページへアクセスしやすいのも特徴です。
裁判所職員の日常についても書かれた貴重な1冊なので、手に取ってみてはいかがでしょうか。
\裁判所職員(裁判所事務官)の仕事内容・職場の雰囲気などに関する情報を詳しくご紹介しています/
(1)裁判所事務官の仕事内容について:【元裁判所事務官が解説】裁判所事務官と裁判所書記官の違いは?仕事内容・お給料・学歴などについて
(2)裁判所事務官の職場の雰囲気について:【元裁判所事務官が詳しく紹介】裁判所事務官の職場環境は?風通しのよさや体育会系なのかについても解説
(3)裁判所書記官試験について:【元裁判所事務官が詳しく紹介】裁判所書記官試験の受験事情
■そのほか、裁判所事務官時代のリアルでニッチな情報はこちらで随時更新中です!