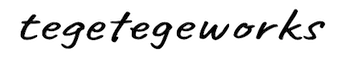2013年4月〜2018年3月まで裁判所事務官(一時期は検察審査会事務官も兼務)として勤務し、現在はライターをしているみさちゅーです。
勤務当時の情報にはなりますが、裁判所事務官志望の方・公務員試験を控えている方に向け、裁判所職員の内部事情や仕事内容などをご紹介しています。
裁判所事務官志望の方のなかには、実際に裁判所で働き始めたあとの自分を想像しながらモチベーションを維持している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、裁判所事務官の仕事内容も詳しくご紹介しながら、裁判所事務官が使うデスクや事務用品についてご紹介します。
裁判所事務官が仕事でよく使う事務用品
書類作成は裁判所事務官の仕事。ノートパソコン・有線マウス・マウスパッドが必需品

ノートパソコン・有線マウス・マウスパッドは必需品。
民事部・刑事部などの事件部に配属された裁判所事務官は、一日の大半を書類作成の仕事に費やしています。
裁判を行う日の決定通知・手続きを始めることを関係者へ通知する書類など、作成する書類の種類はさまざまです。
\裁判所事務官はどうやって書類を作成するの?部署の種類別に紹介/
キーボードやマウスパッドなどは自由に持ち込めた

自分好みのキーボードを持ち込んでいる方もいたので、ウイルス感染の恐れがないものについては、仕事道具の持ち込みは自由な印象でした。
私自身も、貸与のマウスパッドが小さすぎて使いづらく、自分で買って持って行ってました。
\裁判所事務官が使うパソコンや、仕事に必要なITスキルについてはこちら/
裁判所事務官が仕事に使う執務マニュアル・六法は手の届く場所に
デスクには、よく使う執務用のマニュアルも置いていました。
仕事の内容によって分冊されている場合は、よく使うもののみをデスク上、あまり使わないものはデスクの深い引き出しに入れていました。
執務マニュアルと一緒に開くことが多い「六法」もデスク上で保管
出典:Amazon.co.jp
有斐閣の判例六法Professionalも、デスク上で保管していました。
裁判所の事件部(民事部・刑事部など)では、基本的に根拠条文にのっとった仕事が求められるので、執務マニュアルと一緒に六法を開くこともあります。
\六法全書ではなく有斐閣の判例六法Professionalを使用している理由は?/
【元裁判所事務官が詳しく紹介】裁判所事務官が愛用する、判例六法Professionalの魅力。六法全書との違いもチェック
裁判所事務官の仕事に欠かせない「ふせん」も常備
個人的に、裁判所事務官の仕事において、ふせんは欠かせない存在だと思います。
電話で受けた内容の伝達は、ノートサイズのふせんで
出典:Amazon.co.jp
裁判所事務官時代に一番よく使っていたのは、少し大きめのノートサイズのふせんでした。
裁判所事務官の仕事内容のひとつに、電話対応があります。
例えば、弁護士さんなど事件の関係者から電話がかかってきた場合、簡易的なメモでよければふせんに書き込み、口頭での伝達+事件記録に貼り付けることで裁判所書記官へ引き継ぐことも。
また、裁判の日程調整の記録など、残しておきたいけれどしっかりと文章化・データ化する必要がないものも、ノートサイズのふせんに残していました。
\裁判所事務官は突然電話応対を担当させられるのか・電話の相手などをご紹介しています/
伝達事項や進捗具合のメモには75×25mmサイズのふせんが活躍
出典:Amazon.co.jp
情報量が少なく、ちょっとしたメモを作りたいときには、75×25mmサイズのふせんを使用。
例えば、担当書記官への伝達事項がある場合や、進捗状況を共有したい場合などに事件記録へ貼り付けていました。
最終的には裁判官からのゴーサインが必要となるものの、裁判所事務官は基本的に裁判所書記官と二人三脚で仕事を進めていきます。
裁判所書記官が仕事を進めやすいよう、サポートするのも裁判所事務官の仕事内容のひとつだといえるでしょう。
\裁判所にどんな裁判所職員や裁判官がいるのか知りたい方はこちら/
元裁判所書記官の方が書かれた「じつは裁判所ってこんな所なんです!裁判所勤務20年書記官の卒業日記 」には、
元裁判所事務官の私も「あーそうだった!懐かしい!」と感じるリアルな情報がたくさん書かれていました。
お給料や育休関係などの待遇面・組織に関する情報をはじめ、どんな裁判所書記官・裁判官がいるのかが書かれた章もあるので、裁判所職員を目指すなら一読しておくのがおすすめです。
旅費や日当などの決裁にはインデックスサイズのふせん
出典:Amazon.co.jp
資料を決裁に回すときには、インデックスサイズのふせんを使用していました。
民事部や刑事部に配属された場合、証人や裁判員などの旅費・日当を会計課へ申請するのも、裁判所事務官の仕事です。旅費であれば、裁判所から目的地までの距離が分かる地図・請求書案などを作成し、決裁にかけます。
このとき、資料が複数枚にわたるため、どこにどの資料があるかわかりやすいように75×25mmサイズのふせんを使っていました。
ボールペンでは消えてしまうので、油性ペンで書き込むのがポイントです。
裁判所事務官は電話応対の頻度も高め。左右上部のどちらかには電話を設置
出典:Amazon.co.jp
左右上部のいずれか取りやすい場所には電話も置いています。
内線・外線の切り替え機能や番号登録機能などがあり、よくやりとりをするところはあらかじめ登録されていました。
ちなみに、受話器はポンと乗せただけでは上がったままの状態と認識されてしまうので、ガチャっと言わせるまで押す?のがコツです。
デスク本体について
出典:Amazon.co.jp
まずは、裁判所事務官が使うデスク本体についてご紹介します。
裁判所事務官が使うデスクは、お役所でよく見かける事務用のデスク。私が使っていたのはベージュを基調としたデザインでした。
これまでさまざまな方が使ってきているので、角やフチはかなり擦れており年季が入っていました。
デスクには透明で厚めのデスクマットも
出典:Amazon.co.jp
デスクには、透明なデスクマットが敷いてあります。
デスクマットの下には内線番号表や、高頻度で見直すメモなどを入れていました。
また、割と厚めなので、電話応対でメモをとったり手書きで書類を作成したりする場合にも便利でした。
裁判所事務官時代に、デスクを構成するうえで気をつけていたこと
電話対応用のメモ帳とペンは電話の近くに置く

裁判所事務官は、係宛にかかってきた電話をとり、適宜担当者に伝達したり、つないだりするのも仕事内容のひとつ。
電話対応用のメモ帳やペンは、電話の近くに置いていました。
当たり前ですが、電話は作業中に突然かかってきます。置き場所が決まっていなかったり、手に届きにくい場所に置いていたりするとメモがとれません。
個人用印鑑と朱肉はデスクの右上に並べる

個人用印鑑や朱肉も、裁判所事務官が使う仕事道具のひとつ。
主に内部用の書類を作成したり、申請したりするときに使用します。
内部用の書類とはいえ、割と使用頻度が高いので、登庁後はデスクへ出していました。
\裁判所事務官が使う印鑑についてはこちら/
\裁判所職員(裁判所事務官)の仕事内容・職場の雰囲気などに関する情報を詳しくご紹介しています/
(1)裁判所事務官の仕事内容について:【元裁判所事務官が解説】裁判所事務官と裁判所書記官の違いは?仕事内容・お給料・学歴などについて
(2)裁判所事務官の職場の雰囲気について【元裁判所事務官が内部事情を詳しく紹介】職場環境はどんな感じ?
(3)裁判所書記官試験について:【元裁判所事務官が詳しく紹介】裁判所書記官試験の受験事情
■そのほか、裁判所事務官時代のリアルでニッチな情報はこちらで随時更新中です!
【裁判所事務官に興味があるなら、通信講座で気軽に試験対策を始めてみませんか?】裁判所事務官に興味があるものの、ほかの国家公務員・地方公務員も気になっている方におすすめなのが、
法律系の難関国家資格に強い「アガルートアカデミー」が展開する公務員試験講座です。