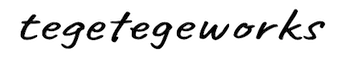2013年4月〜2018年3月まで裁判所事務官(一時期は検察審査会事務官も兼務)として勤務し、現在はライターをしているみさちゅーです。
勤務当時の情報にはなりますが、裁判所事務官志望の方・公務員試験を控えている方に向け、裁判所職員の内部事情や仕事内容などをご紹介しています。
今回は、実際に裁判所で裁判所事務官として働いた経験をもとに、裁判所事務官と裁判所書記官の違いをご紹介します。
裁判所事務官と裁判所書記官の仕事内容の違い
裁判所事務官と裁判所書記官の仕事内容は、配属される部署により異なります。
まず、裁判所は、主に2つの部署に分かれています。
・裁判部門:実際に事件を扱う民事部や刑事部など
・司法行政部門:裁判所で働いている職員に関わる仕事や、裁判所の環境整備を行う(例:総務課・人事課・会計課など)

ちなみに、裁判所事務官をはじめとする裁判所職員の間では、裁判部門は「事件部」・司法行政部門は「事務局」と呼ばれています。
裁判所事務官のほうが仕事の幅は広い。法律に触れつつ事務のエキスパートを目指せる

裁判所事務官の仕事は、法律に触れながら事務のスキルを高められるのが魅力です。
裁判部門のうち、民事部や刑事部などの「事件部」に配属された場合は、裁判所書記官からの指示のもと、事件の受付・事件記録の作成・裁判日程の調整などを行います。
例えば、事件の受付は、ただ受付印を押すだけではありません。
訴状と添付書類を照合して内容の相違がないかチェックしたり、場合によっては電話で相手に問い合わせたりと、さまざまな事務のスキルが必要不可欠な仕事です。
もちろん、パソコンでの受付処理もあり、ひとつの仕事を終えるためには複数の事務をこなす必要があります。
\仕事内容もより詳しくご紹介!適性があるかどうかの参考にも/
裁判所事務官なら、人事・広報・経理などの仕事を担当できることもある

裁判所事務官は、人事・広報・庶務を担当する総務課や、経理・備品の管理に携わる会計課などの「事務局」へ配属されることもあります。
裁判所書記官には専門性が求められる一方、裁判所事務官は幅広いジャンルの仕事にチャレンジしやすいのが特徴です。

実際に裁判所で働いてみて受けた印象としては、裁判所事務官は広く浅く、裁判所書記官は狭く深い仕事。将来的に転職を考えた場合、裁判所事務官を続けるほうが仕事の幅が広がるかもしれません。
裁判所書記官は狭く深い知識が必要。豊富な法律知識で専門性の高い仕事を行う

裁判所書記官は、裁判所事務官より専門性が高い仕事に取り組めるのが強みです。
裁判所書記官になるためには、裁判所事務官として裁判所に入庁後、内部試験に合格しなければなりません。
裁判所事務官が裁判所書記官へステップアップする流れ
- 裁判所内の内部試験をクリアする
- 埼玉県にある「裁判所職員総合研修所(通称「総研」)」へ異動する
- 1〜2年間かけて専門的知識を習得:裁判所の採用試験対策で得た法律知識以上に、専門的な知識が身につきます。
- 必要な課程を修了した後に裁判所書記官として裁判所へ戻る
研修期間は、法学部を卒業している場合は1年、法学部以外を卒業している場合や高卒・専門学校卒の場合は2年です。
条件を満たすと、より短期間の研修で済む「CP枠」でも裁判所書記官の資格が得られます。

裁判所書記官の仕事内容は裁判手続きにかかわるものがほとんどです。
※まれに「裁判所事務官」という肩書きで司法行政部門に送られることもあります。
\裁判所書記官試験について詳しく知りたい方はこちら/
裁判所書記官なら法服を着て法廷で仕事ができる

裁判所書記官になれば、法服を着て法廷で仕事ができます。
法廷に設けられている「法壇」の1段目にいるのは裁判官、2段目にいるのが裁判所書記官です。法廷にいる裁判所書記官は、やりとりの録音や調書作りなど、いろいろな仕事を行っています。

裁判所事務官は法廷での裁判手続きに直接立ち会うことはほぼなく、法服を着る機会もありません。
裁判所事務官の法廷での仕事内容は、法廷での手続きが始まるまでのサポートです。
法廷に貼り出されている裁判の日程表を作成・掲示したり、事件の内容によっては法廷についたてを置いたりすることもあります。
\法廷での裁判所事務官の仕事内容はこちら/
裁判所事務官・裁判所書記官の仕事内容を詳しく知りたい方におすすめの1冊

※出典:Amazon.co.jp
裁判所事務官や裁判所書記官の仕事内容について詳しく知りたいなら、法学書院編集部「裁判所事務官・裁判所書記官の仕事がわかる本(公務員の仕事シリーズ) 」もおすすめです。
「裁判所事務官・裁判所書記官の仕事がわかる本(公務員の仕事シリーズ) 」の魅力的なポイント
■裁判所事務官の1日の流れがわかる
■民事・刑事・家事(家庭裁判所関連)手続きで行う裁判所書記官の仕事も紹介されている
■求められる人物像・合格体験記なども掲載されている
入庁後のイメージを膨らませることで、受験勉強のモチベーションを上げたいときにも役立つでしょう。
裁判所事務官・裁判所書記官の学歴面での違いは?

採用前においては、裁判所事務官と裁判所書記官の学歴面の違いはありません。
裁判所書記官になるには、一度「裁判所事務官」として裁判所へ入庁する必要があるためです。
裁判所事務官としての入庁後は、裁判所内の内部試験をクリアし、裁判所職員総合研修所での課程を修了したのち、はじめて資格を得られます。

ただし、法科大学院(ロースクール)出身者のほうが、裁判所書記官試験への合格にかかる年数は短い傾向にあります。
高卒・専門学校卒でも、努力次第で裁判所書記官になれる

大卒以上の人と同様、高卒・専門学校卒で入庁した裁判所事務官も、一定期間働けば裁判所書記官試験が受けられます。
高卒・専門学校卒で入庁する場合は、受験時に法律知識が必要ないケースがほとんど。高卒・専門学校卒では、裁判所書記官を目指せないのではないかと思っている方も多いのではないでしょうか。

個人的には、裁判所は高卒・専門学校卒の採用人数が少ないわりに、裁判所書記官になっている方は多い印象でした。
最終学歴に関係なく、裁判所内での勉強会などを通じて試験対策ができる場合もある

裁判所によっては、最終学歴に関係なく裁判所内での有志による勉強会を通じて試験対策ができる場合もあります。
また、先輩からおすすめの本を教えてもらえたり、分からないことを解説してもらったりしている方もいました。
また、裁判所では学歴を問わず「同期」とする文化もあるので、同期と一緒に楽しく勉強するのもおすすめです。
\裁判所事務官の採用幅についてはこちら/
裁判所事務官と裁判所書記官のお給料や待遇には違いがある?

裁判所事務官と裁判所書記官では、お給料に違いがあります。裁判所書記官のほうが手当がつくため、もらえる金額は上がります。
待遇に関しては、違いを感じることはありませんでした。
\裁判所事務官のお給料については以下でご紹介しています/
法律+事務を幅広く扱うなら裁判所事務官。法律に深く関わるなら裁判所書記官
裁判所事務官と裁判所書記官、自分はどちらが向いているんだろうと思う方もいるでしょう。
裁判所事務官と裁判所書記官のどちらがおすすめかどうかは、どんな仕事をしたいかどうかにより異なります。
■裁判所事務官:法律や法的手続きに触れながら、事務のスキルを養成・活用していきたい方におすすめ
■裁判所書記官:法廷での仕事や法服に憧れがある方・法的手続きに関わる仕事を中心に行いたい方におすすめ
今回は、元裁判所事務官が考える裁判所事務官と裁判所書記官の違いをご紹介しました。

裁判所書記官を目指す場合でも、一度は裁判所事務官として働くことになります。実際に裁判所事務官として仕事をしながら、自分の適性や今後の働き方を考慮し、キャリア形成が行えると理想的です。
\裁判所職員(裁判所事務官)の仕事内容・職場の雰囲気などに関する情報を詳しくご紹介しています/
(1)裁判所事務官の仕事内容について:【元裁判所事務官が解説】裁判所事務官と裁判所書記官の違いは?仕事内容・お給料・学歴などについて
(2)裁判所事務官の職場の雰囲気について【元裁判所事務官が内部事情を詳しく紹介】職場環境はどんな感じ?
(3)裁判所書記官試験について:【元裁判所事務官が詳しく紹介】裁判所書記官試験の受験事情
■そのほか、裁判所事務官時代のリアルでニッチな情報はこちらで随時更新中です!
【裁判所事務官に興味があるなら、通信講座で気軽に試験対策を始めてみませんか?】裁判所事務官に興味があるものの、ほかの国家公務員・地方公務員も気になっている方におすすめなのが、
法律系の難関国家資格に強い「アガルートアカデミー」が展開する公務員試験講座です。